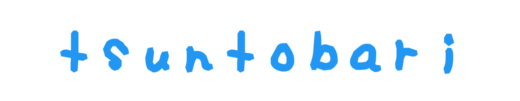「NISAって、どこで始めたらいいの?」
証券会社ってたくさんあって、正直どこを選べばいいのか迷いますよね。僕が最初にぶつかったのも、まさにこの疑問でした。
銀行でも作れるらしいし、ネット証券ってなんだか難しそう…。 でも調べてみたら、今は「ネット証券」が断然おすすめでした。
この記事では、証券会社ごとのちがい、選び方、そして僕が楽天証券を選んだ理由までまとめます。 「放置でも大丈夫?」「続けられる?」そんな不安がある方にも、僕の体験が少しでも参考になればうれしいです。
※2023年までの「つみたてNISA」は、2024年から新NISAの「つみたて投資枠」として統合されました。この記事では、このつみたて投資枠を中心に、証券会社の違いや選び方を紹介しています。
そもそも、どこでNISA口座って作れるの?
NISA口座は、以下のような金融機関で開設できます。
- 楽天証券やSBI証券などのネット証券
- 野村證券や大和証券などの店舗型証券会社
- ゆうちょ銀行や地方銀行などの銀行窓口
選択肢はたくさんありますが、初心者にとってはネット証券が圧倒的に使いやすいです。
銀行や窓口型の証券会社ではダメなの?
「対面で相談できるから安心」と思うかもしれません。 でも、デメリットもあります。
- 商品の選択肢が少ない
- 手数料が高いことがある
- 投資信託の選び方を“営業”されることも…
一方でネット証券は、商品の自由度が高くて、手数料も安い。それに、アプリやサイトで気軽に管理できるのも魅力です。
銀行とネット証券の違いを簡単に比較してみました:
| 比較項目 | 銀行・窓口型 | ネット証券 |
|---|---|---|
| 商品数 | 限られていることが多い(数十本) | 非常に豊富(数百本〜) |
| 手数料 | やや高め | 基本的に低コスト |
| サポート | 対面あり(安心) | チャットや電話などオンライン中心 |
| アプリ・サイトの使いやすさ | 限定的 | 操作しやすく、管理がしやすい |
| クレカ積立 | 非対応が多い | 対応している会社が多い |
証券会社を選ぶときのチェックポイント6つ
とはいえ、証券会社ごとの違いってぱっと見ではわかりづらいですよね。
でも、選び方にはいくつかの“基準”があります。 まずは「どこで口座を開くか?」を選ぶことが大切です。
証券会社によって使いやすさやサービスが違うので、ここを間違えると途中で挫折してしまうことも。 そんな後悔をしないために、以下のポイントをチェックしてみてください。
- スマホでも使いやすいか
- クレジットカードで積立できるか(ポイント還元)
- 投資信託の取り扱いが豊富か
- ポイントを使って投資ができるか
- 手数料は低いか
- 口コミやサポート体制は安心できるか
これらのポイントをチェックすることで、自分に合った証券会社が見つけやすくなります。 特に「クレカ積立」や「ポイント投資」は、初心者でもお得感を感じながら続けやすい仕組みです。
【比較表】主要ネット証券のクレジットカード積立サービス(2025年時点)
ここでは、具体的にどの証券会社がどんなサービスを提供しているのかを比較してみます。特に「クレジットカードでの積立」や「たまるポイント」「ポイントの使い道」は、実際に運用を続けていくうえで重要なポイントです。
| 証券会社 | 商品数 | 還元率 | たまるポイント | 投資にポイント利用 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 267本 | 0.5〜2.0% | 楽天ポイント | 可(そのまま使える) |
| SBI証券 | 271本 | 0〜3.0% | Vポイント | 可(Vポイント投資対応) |
| マネックス証券 | 264本 | 0.73〜3.1% | マネックスポイント | 不可(ギフト券など交換のみ) |
| 松井証券 | 266本 | 0.5〜1.0% | Oki Dokiポイント | 不可(直接利用は不可) |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 253本 | 0.5〜2.0% | Pontaポイント | 可(そのまま使える) |
こうした条件を比較しておくことで、あとから「知らなかった…」と後悔することも減ります。 それぞれの証券会社の特徴がはっきり見えてきたでしょうか?
もし「まだ決めきれない…」という方は、次のように自分に合ったタイプで選んでみるのもおすすめです:
- 楽天証券:楽天ポイントを使いたい、楽天市場ユーザーにおすすめ
- SBI証券:とにかく商品数を重視したい、iDeCoと併用したい人に
- マネックス証券:還元率1.1%を重視したい人(ただしポイントの使い道は限定)
- 松井証券:電話などのサポートを重視したい人に
放置でも大丈夫?NISAは“仕組み”がすべて
NISAって、始めたはいいけど「ほんとに放置でいいの?」って、ちょっと不安になりますよね。
でも安心してください。新NISAの「つみたて投資枠」は、そもそも“自動でコツコツ続ける”ために作られた制度なんです。
一度設定すれば、あとは毎月自動で積み立ててくれる仕組みになっていて、細かい操作や相場チェックは不要。
頻繁に売買したり、タイミングを計る必要がないので、相場に一喜一憂せずに続けられるのも特徴のひとつです。値動きを見て焦ったり、一喜一憂する必要もありません。
むしろ、「気にしすぎずに放っておけること」が、長く続ける最大のコツ。
実際に僕も、月に一度くらい確認するだけ。それでもちゃんと資産が積み上がっていくんです。
楽天証券を選んだ理由
ここからは、実際に僕がNISAを始めたときの体験談を紹介します。
いろいろな選択肢がある中で、最終的に楽天証券を選んだ理由とは?
楽天証券は、NISA口座数が600万口座を超えていて、業界No.1の実績があります(2024年12月時点)。「NISAを始めるなら楽天」と言われるのも納得で、実際に多くの人がここからスタートしています。
僕がNISAを始めたとき、クレジットカードで積立できたのは楽天証券だけでした。 しかも、楽天カードで積み立てると1.0%分の楽天ポイントがもらえる。
「え、普通に投資してるだけでポイントもらえるの?」そんな感覚で、めちゃくちゃお得に感じました。
あと、アプリが直感的で使いやすいのも助かりました。 ポイントもそのまま投資に使えるし、楽天市場のポイントが増えてくるとそれを運用に回せる。 楽天経済圏にいる人には、ほんとに相性いいと思います。
正直、最初は「積立NISAって放置でいいのかな?」という不安もありました。
でも楽天証券ならクレカ積立で自動化できるし、アプリでたまに残高をチェックするだけでOK。仕事で忙しい時期でもほったらかしで続けられたので、今では「始めてよかった」と思っています。
まとめ:迷ったら、まずは楽天証券かSBI証券でOK
証券会社選びに時間をかけすぎるより、「早く始めて、コツコツ積み立てる」ほうが将来的なリターンにつながります。
- クレカ積立でポイントが貯まる
- 投資にポイントも使える
- アプリが使いやすくて、手数料も安い
このあたりをクリアしているのが、楽天証券とSBI証券です。どちらも多くの人に選ばれている証券会社です。
楽天証券はNISA口座数No.1、SBI証券は総合口座数No.1という実績があるので、はじめてでも安心して選べます。
\ 今すぐ始めたい方はこちら /
楽天証券でNISAを始める(NISA口座数No.1)
SBI証券でNISAを始める(総合口座数No.1)
NISAは一度設定すれば、ほったらかしでもしっかり資産が積み上がっていきます。忙しくて投資に時間をかけられない人ほど、早めに始めて「自動で増える仕組み」を作っておくのがおすすめです。